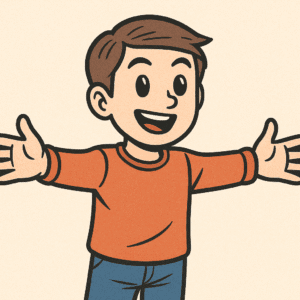「Don’t hesitate.」
英語ではよく見かけるこの表現は、「遠慮しないで」と日本語に訳されることがあります。けれど、実際に日本の食卓で「遠慮しないでね」と言われたとき、その言葉にはどんな気持ちが込められているのでしょうか。そして、それを「Don’t hesitate.」と訳して、本当に伝わるのでしょうか。
私たちは翻訳をする際、つい「言葉=意味」だと考えてしまいがちです。単語と単語を対応させ、文法を整えれば、それはもう翻訳だと思ってしまう。けれど、言葉には、単なる意味以上のもの——その言葉が生まれた文化、空気、感情、関係性が含まれています。
たとえば、「遠慮」という言葉には、相手に迷惑をかけたくない気持ち、自分が前に出過ぎないための慎み、そして、相手の立場や場の調和を尊重するという感覚が込められています。英語の "Don’t hesitate" は、たしかに「ためらわずにどうぞ」という意味ですが、それは「恥ずかしがらないで」「自信を持って」というような、自己表現を促す表現に近く、日本語の「遠慮」のような他者への配慮を中心とした感覚とは、どこかずれているのです。
翻訳の難しさは、まさにこうした「言葉の奥にある感性」をどう伝えるか、というところにあります。言葉の意味だけを伝えるなら辞書で十分。でも、その言葉がどんな場面で、どんな人間関係の中で、どんな気持ちで使われているかを伝えるには、相手の文化の中で通じる別の形で表現しなおす必要があるのです。
これは、白という色を知らない人に「白」を説明するのに似ています。たとえば視覚に障害がある人に、雪の白さや雲の白さを言葉だけで伝えようとしたとき、「白はこういう色です」と説明するだけでは足りません。代わりに、「冷たい空気に触れたときの感覚」や「朝の静けさ」といった、相手が知っている別の感覚を手がかりにして、近いイメージを構築するしかないのです。
「遠慮」も同じです。文化の中で当たり前のように使われている言葉は、そのまま別の文化に持ち込むと、意味が通じないどころか、誤解されてしまうことすらあります。だから翻訳者は、言葉そのものを訳すのではなく、「なぜその言葉がそこにあるのか」を理解し、それを異なる文化の中でどう生きた意味にするかを考える必要があります。
翻訳は、単なる置き換えではありません。
それは、他者と関わろうとする試みであり、異なる世界に橋をかける創造的な行為です。完全な翻訳など存在しないかもしれません。けれど、完全ではないからこそ、私たちは「どう伝えるか?」と問い続けることができるのです。
「遠慮」は翻訳できるか?
その問いに簡単な答えはありません。でも、その問いを通して、私たちは自分自身の文化のあり方を見つめ直すことができます。そして、他者とわかり合いたいと願う気持ちが、翻訳という行為をより豊かにしてくれるのだと思います。