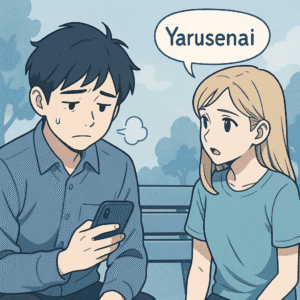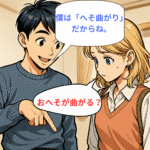ある日の大学。ヒロシはスマホで昔の音楽を聴いていた。笑いをこらえながらイヤホンを外す。
ヒロシ: エミリー、これ知ってる?「ひねってワオ!」ってやつ。昔のパロディバンド、「王様」ってバンドの曲なんだけど。
エミリー: へぇ、知らないなぁ。
ヒロシ: 洋楽の『Twist and Shout』ってあるでしょ?あれの “Come on baby” を「おいでおいで、赤ちゃ〜ん!」って直訳して歌ってるの。もう笑いが止まんなくてさ。
エミリー: どれどれ、ほんとだ。面白いわね。でも…ちょっとわかるかも。“baby”って、日本語では「赤ちゃん」って意味しかないもんね。
ヒロシ: そうそう。オレ、“baby”って呼ばれる恋人とか、マジで想像つかないんだよ。「赤ちゃん!」って言われても…甘えん坊な彼女?それともほんとにオムツの人?ってなる(笑)
エミリー: でも英語では、“baby”は恋人への愛称としてすごく普通だよ。大事に思ってるとか、守ってあげたいって気持ちがこもってる。
ヒロシ: へぇ…そう言われるとそうなんだろうけど、オレの頭には“赤ちゃん”のイメージが焼きついちゃっててさ。
エミリー: うん、わかる。でもね、実は私も似たような体験あるよ。
ヒロシ: え?エミリーもあるんだ?
エミリー: 日本語の「神」って言葉。最初、すごく神聖で宗教的な意味しかなかったんだけど、日本に来たら「神対応」とか「神アニメ」とか、やたら日常的に出てきてびっくりした。
ヒロシ: あ〜、あるある。でも日本語だと「神」って、単に“すごい!”って意味にもなるんだよね。
エミリー: 今ではわかるけど、最初はほんとに違和感あった。「えっ、そんな軽く神って言っていいの!?」って(笑)
ヒロシ: なるほどな…オレが「赤ちゃんに愛をささやくの無理!」って思うのと同じかも。
エミリー: うん、たぶんお互い「最初に覚えた意味」に引っ張られてるんだよね。言葉の“感覚”って、頭だけじゃなくて身体で覚えてる気がする。
解説
ヒロシが“baby”に違和感を覚え、エミリーが“神”に戸惑った──
このふたりの反応は、まったく逆のように見えて、実は非常によく似ている。
どちらも共通しているのは、言葉を最初に学んだときの“意味のイメージ”が強く刷り込まれているという点だ。
たとえば、“baby”を「赤ちゃん」として覚えた日本人にとって、
恋人への呼びかけとして使われる“baby”は「未熟な存在」「守られる側」という印象が強すぎて、
愛情表現として自然に受け取ることが難しい。
一方、“神”という言葉を「God=唯一神」として理解していたエミリーにとって、
「神対応」や「神アニメ」といった日常語としての使い方は、軽すぎて戸惑いを覚える。
自分の中で「神=絶対的な存在」「畏れの対象」という感覚があるからだ。
このように、私たちは言葉を“意味”だけでなく、“感覚ごと”覚えている。
しかも、最初に学んだ意味が強烈であるほど、その印象に縛られてしまう。
語学ではよく「文脈で意味をつかもう」と言われるが、
実際に“文脈”で使われている例に出会っても、最初に持ったイメージとのギャップがあると、それを受け入れるのが難しくなる。
だから、baby や 神 のように、
本来は“深い感情”や“強い評価”を込めた言葉であっても、
文化をまたいで使われたときに「えっ?」という違和感が生まれるのだ。
ここで重要なのは、言葉そのものが悪いわけではないということ。
問題なのは、「ひとつの意味に固定して覚えてしまう」ことであり、
さらに言えば、その背景にある文化や価値観を見落としてしまうことだ。
baby は「赤ちゃん」だけではない。
恋人への愛情、親密さ、かわいさ、守りたい気持ち──
そうした感情が込められた呼びかけでもある。
神 も「宗教的存在」だけではない。
日本語では、「最高」「完璧」「人智を超えてすごい」といった賞賛の表現として拡張されている。
こうした意味の広がり方は、それぞれの文化の中で自然に育ってきたものであり、
私たちが言葉を学ぶときには、「語彙」だけでなく「文化の感覚」ごと受け取ることが必要になる。
つまり、
言葉に宿る“文化のちがい”を知ること。
それは単語を覚えることではなく、
その言葉がどんなふうに“感じられているか”を理解することなのだ。
英語での補足解説
In English, "baby" is commonly used as a sweet nickname for someone you love. But in Japanese, the word “赤ちゃん” (akachan) is strongly associated with helpless infants. This makes it hard for many Japanese learners to emotionally connect with "baby" as a romantic term.
On the flip side, Japanese people often use the word “神” (kami, god) to describe something amazing: like "神アニメ" (god-tier anime) or "神対応" (godlike customer service). This casual use of a sacred term often confuses English speakers, who associate “God” with religious reverence.
Both cases reveal how language learning is not just about translation—it’s about cultural perception.
🗣 日本語訳
英語では、“baby” は恋人を呼ぶ甘い愛称としてごく自然に使われます。
しかし、日本語の “赤ちゃん” という言葉は「無力で小さい存在」というイメージが強く、
多くの日本人学習者にとって、“baby” を恋愛表現として受け入れるのは難しいのです。
逆に、日本語では「神」という言葉を「神アニメ」「神対応」のように
“すごい”や“完璧”といった意味で日常的に使います。
ですが、英語話者にとって “God” は宗教的・神聖な存在なので、
そうしたカジュアルな使い方に戸惑いを覚えることがあります。
このように、どちらのケースも、単語の意味だけでなく
文化的な受け取り方そのものが言語理解のカギとなっているのです。
以下の表は、「名詞/動詞/形容詞」といった品詞分類にこだわらず、
日本語と英語で“意味”ではなく“感覚”がズレる言葉たちを一望できるようにまとめたものです。
| 英語表現 | 日本語での直訳・刷り込み | 英語での実際の使われ方 | 日本人が感じるズレ・違和感 |
|---|---|---|---|
| baby | 赤ちゃん | 恋人・甘えた呼びかけ | 幼児イメージが強く、恋人に使うと気持ち悪く感じる |
| God | 神様 | 畏敬だけでなく、驚きや称賛にも使う(Oh my God! / You’re a god!) | 宗教的な重みがある言葉を軽く使われると抵抗がある |
| smart | スリム・かっこいい(見た目) | 頭が良い、知的に見える | 外見だと思ったら知性の話だった、逆にとらえてしまう |
| love | 愛してる(重い) | 「大好き」レベルでも気軽に使う(I love coffee) | 「そんなに言うほど!?」と違和感、重すぎ・軽すぎ両方でズレる |
| miss | ~がいなくて寂しい | 人だけでなくモノや習慣にも(I miss summer) | 「会いたい」ではなく「戻りたい感」への理解が難しい |
| cool | 冷たい? / かっこいい(見た目) | 状況や考え方、人への評価にも使う(That’s cool!) | 「何が冷たいの?」と混乱、意味の幅が広くて読み取りにくい |
| tired | 疲れている | 相手を気づかう優しい言葉(You look tired.) | 「見た目が疲れてる」と言われたように感じてネガティブに受け取る |
| sweetheart / honey | 甘い/食べ物系 | 恋人・パートナーへの愛称 | 食べ物→人、の転用に戸惑い、「気持ち悪い」と感じることも |
| dude / man / bro | 男、やつ、兄弟 | カジュアルな呼びかけ、友情表現 | 直訳すると乱暴に見える。意味よりもトーンが大事なのに誤解されがち |
| angel | 天使(宗教・空想) | 大切な人・守ってくれる人への褒め言葉 | 現実の人間に使うと「大げさすぎ」「中二病?」と感じることも |
最後に
“baby”に違和感を覚える、その正体は──
- 最初に覚えた意味が刷り込まれているから
baby = 赤ちゃん、というイメージがこびりついている。 - 文化や使われる場面を知らないから
恋人に使う“baby”がどんな気持ちで発せられているかを知らない。 - 言葉を「意味」でしか覚えていないから
言葉に宿る感情・温度・トーンまで受け取れていない。
「baby」が恋人への呼びかけになるのも、
映画や音楽の中で何度も耳にして、
その“空気”ごと受け取っていくうちに、少しずつ体にしみこんでいく。
言葉は辞書でなく、会話の中で育つ。
だからこそ、
ネイティブの言葉を、観察し、まねて、感じてみることが近道なんだと思います。