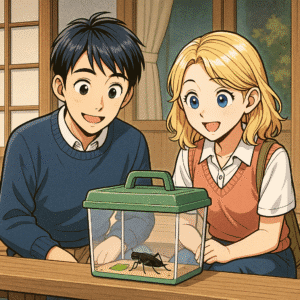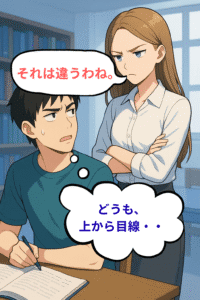言葉がわかりすぎると、映画はつまらなくなる?
このサイトでは、「日本語と英語の感覚の違い」や「言葉に宿る文化のちがい」をテーマにしていますが、最近ふと、映画を観ながらこんなことを思いました。
日本映画って、なんだかしらけてしまうことが多い。それは、日本映画は面白くない。
と一言で片付けていました。もちろん作品によるし、ストーリーや演出が良ければ感動することもあります。でもどうも、韓国映画や英語の映画のほうが、没入しやすいと感じる。
その理由のひとつが、「日本語がわかりすぎる」ことにあるんじゃないかと思ったんです。
たとえば、セリフの語尾ひとつ。「だよね」「でしょ」「そうじゃない」「だろ?」……。
この些細な言葉の違いだけで、空気感も、緊張感も、本気度もまるで変わってしまうのが日本語です。
だからこそ、「そんな言い方しないよな」とか「なんか芝居がかってるな」と感じてしまうと、一気に冷めてしまう。
つまり、日本映画を観る私たちは、映画に対して非常にシビアな目を持ってしまっているのかもしれません。
一方、韓国映画は韓国語。英語映画は英語。
意味は字幕で理解していても、セリフの“生っぽさ”や“わざとらしさ”までは、言葉としては感じない。
つまり、言葉がわからないからこそ、没入できる部分があるのかもしれません。
翻訳字幕も、実は重要な役割を果たしています。
訳す人が、話のトーンやキャラに合うように調整してくれているからこそ、自然に感じられる。
いわば、翻訳も映画の一部。脚本の裏方のような存在です。
逆に、自分が英語の映画を吹き替えで観たとき、「そんな日本語ある?」と思ってしまうことがあります。
たぶん、英語ネイティブのエミリーが、英語映画の字幕を見たら、同じように「ニュアンスが違うな」と感じるかもしれません。
でもここでひとつ思ったのは、日本映画の監督や脚本家は、それだけ過酷な土俵に立っているのではないかということです。
日本語で映画をつくるということは、日本語ネイティブの観客に“セリフのすべて”が聞こえてしまうということ。
ちょっとした語尾のトーン、間の取り方、言い回しのクセ、どれも見逃されない。
それだけに、「言葉の使い方」で失敗すれば、リアリティは一瞬で崩れます。
つまり、日本映画の制作者は、「翻訳に助けられることのない世界」で戦っているんです。
これは逆にすごいことです。
外国語の映画では、多少セリフが不自然でも、字幕の調整でごまかせる余地がある。
でも日本映画は、セリフの“生の響き”がダイレクトに伝わる分、演技にも言葉にも逃げ場がない。
それでもときどき、日本映画で心を打たれる場面があります。
それは、やはり言葉が「ぴったり」だったとき。
言葉と演技が一致し、音と感情が自然につながったとき、私たちは深く共感し、感動します。
ふと思ったんです。
いい映画、悪い映画も、言葉が重要な鍵になっているんじゃないか?
ストーリーがいくら良くても、セリフがわざとらしいと興ざめする。
逆に、何気ないひと言が、本当に心に残ることもある。
言葉の力ってすごい。
そして、その“言葉”をどう受け取るかで、映画の見え方すら変わる。
そんな気づきもまた、「言葉の面白さ」のひとつだなと思っています。